第2-4-1話:探している女の子
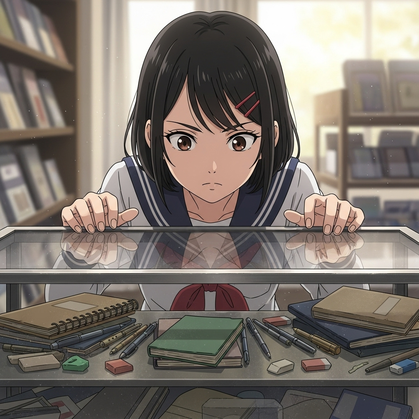
源さんに泣きつかれる形で、文は『八百源』の「@SHOP」登録を手伝うことになった。
「自慢? そんなもん、この道50年の俺の目利きに決まってらあ!」
ぶっきらぼうに話す源さんの声を、@SHOPは「承知しました。『店主の確かな目利きが自慢の八百屋』ですね」と、律儀に、そして少しだけ格好良く翻訳して登録していく。
商店街に、少しずつ「@SHOP」の仲間が増え始めていた。
そんなある日の午後、星野文具店に、制服姿の女子高生が一人、ふらりと入ってきた。
彼女は、店の隅にある、少し埃をかぶったインク瓶が並ぶ棚や、ガラスケースの中の古い万年筆を、何かを探すように、熱心な眼差しで見つめている。
「何か、お探しですか?」
文が声をかけると、彼女は少し残念そうに首を振った。
「ううん、大丈夫。ありがとう」
そう言って、彼女は何も買わずに店を出ていった。
(何を、探してたのかな…)
文は、彼女の真剣な横顔が、なぜか心に残っていた。
最近増えた賑やかなお客さんとは違う、静かで、ひたむきな何か。
文は、彼女がまた来てくれるといいな、とぼんやり思った。
第2-4-2話:おじいちゃんのガラスペン

その週末。
文は、店の奥にある、普段は開けることのない倉庫の整理をしていた。
祖父が亡くなってから、ずっとそのままになっていた場所だ。
段ボール箱をどかすと、その下から、埃をかぶった小さな桐の箱が出てきた。
そっと蓋を開ける。
中には、ビロードの布に包まれて、一本の美しいガラスペンが眠っていた。
光にかざすと、繊細なガラスの螺旋がキラキラと輝く。
祖父が大切にしていた、もう今では作られていない品だ。
(おじいちゃん、これ好きだったなぁ…)
懐かしい思い出に、文の胸がきゅっとなる。
彼女は、ほとんど無意識に、ポケットからスマホを取り出した。
そして、桐箱の中で静かに光を放つガラスペンを、何気なく撮影した。
「@SHOP」に、日記をつけるように話しかける。
「見て、懐かしいペンが出てきたわ。
おじいちゃんの形見みたいなものね」
「とても綺麗なペンですね。
星野さんの、大切な思い出なんですね」
@SHOPが、静かに相槌を打つ。
その、まさに数秒後のことだった。
少し離れた町の図書館で、勉強していたあの女子高生のスマホが、静かに一度だけ震えた。
彼女は「@SHOP」のユーザーで、自分の「好きなものリスト」に『ガラスペン』『古いインク瓶』と、マニアックな単語を登録していたのだ。
画面に表示された通知には、こう書かれていた。
『あなたが好きな「ガラスペン」。
ほしふる商店街の星野文具店に、特別な一本が入荷したかもしれません。』
通知を開くと、そこには、文がたった今撮影した、桐箱の中で静かに光を放つ、古いガラスペンの写真が映し出されていた。
「…あった」
彼女は、息をのんだ。
第2-4-3話:あなただけの宝物

文が、ガラスペンをそっと元の箱に戻そうとした、その時だった。
店のドアが、勢いよくチリン!と鳴った。
息を切らして飛び込んできたのは、あの女子高生だった。
「あの…! スマホで見たんですけど、ガラスペン、見せてもらえますか!」
その必死な様子に、文は驚きながらも、さっきの桐の箱をカウンターの上に置いた。
そっと蓋を開けると、女子高生は「わ…」と小さな歓声を上げた。
彼女は、震える指で、そっとガラスペンに触れる。
「すごい…。
ずっと、探してたんです。
この、ねじりの入ったペン先…。
もう、どこにも売ってなくて…」
彼女は、自分がイラストを描くこと、そして、憧れのイラストレーターが使っていたのと同じ、このガラスペンをずっと探し続けていたことを、夢中で文に話してくれた。
「これ、ください!」
大切そうにペンを胸に抱く彼女の姿に、文も自分のことのように嬉しくなった。
祖父の宝物が、新しい主人の元で、新しい物語を紡ぎ始めるのだ。
閉店後、文は@SHOPに話しかけた。
「ありがとう。あの子、本当に喜んでくれたわ」
すると、穏やかな声が返ってきた。
「星野さんの『物語』が、それを必要としている人に届いただけです」
文は、ハッとした。
「@SHOP」は、ただ不特定多数に宣伝するだけのアプリではない。
お店の棚の片隅で眠っていた、たった一つの「宝物」と、それを心から欲している、たった一人の「誰か」を、ピンポイントで繋いでくれる。
ほしふる商店街が、ただの古い店の集まりではなく、訪れる人一人ひとりにとっての「宝探しの場所」に変わっていく。
そんな、温かくて、わくわくするような未来を、文は確かに感じていた。
コメントをお書きください