第1-12-1話:“前例”という名の壁

株式会社テックフォレストでは、来期の予算編成の季節がやってきていた。
マネージャーの佐藤理恵は、高橋健太が発案した新しいアプリ開発プロジェクトの予算案を手に、事業部長のデスクの前に立っていた。
成功すれば、会社の新しい柱になりうる、重要なプロジェクトだ。
「…というわけで、このプロジェクトには、これだけの予算が必要です」
佐藤が説明を終えると、事業部長は、彼女が提出した資料に一瞥をくれただけで、渋い顔をした。
「佐藤くん。この予算額は、君のチームの前年度のプロジェクト予算より30%も多いじゃないか。
うちは、そんなに余裕があるわけじゃないんだ。前例に倣って、もう少し、どうにかならないのかね」
「しかし、部長。今回は、新しい技術を採用するため、どうしても…」
「前例がない、と言っているんだ。現場の工夫と根性で、なんとかするのが君の仕事だろう」
事業部長は、それだけ言うと、別の書類に目を落としてしまった。
佐藤は、唇を噛み締めながら、彼の部屋を後にするしかなかった。
彼女は知っている。
この会社では、予算の承認は、そのプロジェクトの重要性よりも、声の大きさや社内政治の力関係で決まることが多い。
(このままじゃ、高橋くんの素晴らしいアイデアを、不十分なリソースで潰してしまう…)
彼女は、自分のデスクに戻ると、どうすればこの「前例」という名の分厚い壁を壊せるのか、暗い気持ちで考え込んでいた。
第1-12-2話:“未来”の損益計算書
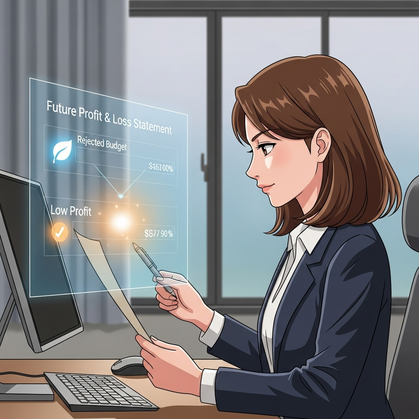
佐藤が、予算を削減するために、どの機能を諦めるべきか、苦渋の決断を迫られていた、その時だった。
彼女のPCに、『ワンチーム』から通知が届いた。
『インサイト:申請中のプロジェクト予算案について。
現在の仮承認額では、計画された仕様に対してリソースが著しく不足しており、75%の確率でプロジェクトの遅延、または品質の大幅な低下が予測されます』
その通知には、続きがあった。
『対策案として「データ駆動型・予算要求レポート」を生成しますか?
社内外の類似プロジェクト実績データを元に、客観的な投資対効果を算出します』
佐藤が「はい」を選択すると、すぐに新しい予算案が生成された。
それは、単なる要求リストではなかった。「未来の損益計算書」とでも言うべき、二つの未来予測だった。
【シナリオA:標準予算(現行案)で進めた場合】
・開発期間:3ヶ月遅延
・実装機能:計画の70%
・リリース後のバグ発生率:28%
・3年後の予想収益:6,000万円
【シナリオB:最適予算(申請案)で進めた場合】
・開発期間:計画通り
・実装機能:計画の100%
・リリース後のバグ発生率:3%
・3年後の予想収益:1億5,000万円
レポートの最後は、こう締めくくられていた。
『本件は、単なるコストの問題ではなく、どちらの未来に投資すべきか、という経営判断の問題であると分析します』
佐藤の目に、強い光が戻った。
彼女は、そのレポートを手に、再び事業部長室のドアをノックした。
第1-12-3話:“数字”が語る優しさ

「部長、もう一度だけ、お時間をいただけますでしょうか」
再度の訪問に、事業部長はあからさまに嫌な顔をした。
だが、佐藤の自信に満ちた表情に、何かを感じ取ったようだった。
佐藤は、感情的に訴えることはしなかった。
ただ、スクリーンに、『ワンチーム』が作成した二つの未来予測を映し出した。
「部長。
私は、予算を増やしてほしい、とお願いしているのではありません。
どちらの未来に、会社として投資すべきか、ご判断をいただきたいのです」
彼女は続けた。
「標準予算という“前例”に従えば、私達は6,000万円の未来しか作れません。
ですが、最適な投資をしていただければ、私達は、1億5,000万円の未来を創り出すことを、このデータと共にお約束します」
事業部長は、腕を組んだまま、食い入るように画面を見つめていた。
彼の言語は、「根性」や「前例」ではない。
「利益」と「損失」だ。
『ワンチーム』のレポートは、完璧に、彼の言語で語りかけていた。
長い沈黙の後、彼は、静かに、しかし力強く言った。
「…わかった。その、最適予算とやらを承認しよう。
だが、必ず、この数字以上の結果を出すんだぞ」
佐藤は、深く、深く頭を下げた。
オフィスに戻り、予算が承認されたことをチームに伝えると、高橋をはじめ、メンバーたちから歓声が上がった。
佐藤は、自分のPCで、静かに佇む『ワンチーム』のロゴを眺めていた。
システムの優しさとは、時に、人間が感情や慣習で曇らせてしまう「事実」を、静かに、しかし、誰にも否定できない「数字」という言葉で、まっすぐに示してくれることなのかもしれない。
それは、チームの未来を守るための、最も賢く、そして力強い優しさだった。
コメントをお書きください