第1-2-1話:消えかけた“光”

『ワンチーム』の導入以来、テックフォレストのチームは順調そのものだった。
特に、高橋健太は、自分の得意なUIデザインの分野で才能を発揮し、生き生きと仕事に取り組んでいた。
マネージャーの佐藤理恵も、彼の活躍に目を細めていた。
だが、新しいプロジェクトが始まり、状況は少しずつ変わっていった。
高橋は、システムの根幹に関わる、プレッシャーの大きなコンポーネントの開発を任された。
期待に応えようと、彼は懸命に仕事に取り組む。
しかし、頻繁な仕様変更とタイトなスケジュールの間で、彼の心身は知らず知らずのうちに摩耗していった。
佐藤は、高橋の顔色が優れないことに気づいてはいた。
チャットでの返事が素っ気なくなったり、彼の書くコードにケアレスミスが増えたりしていることも。
(…少し、疲れが溜まっているのかしら。
でも、彼なら乗り越えてくれるはず)
彼を信頼しているからこそ、下手に干渉してプライドを傷つけたくない。
佐藤はそう考え、静かに見守ることにした。
しかし、高橋の心の中では、自信という光が、今にも消えかけていた。
彼は、ただ誰にも弱音を吐けないまま、一人きりで、終わりの見えないトンネルを歩いているような気分だった。
第1-2-2話:“得意”の処方箋
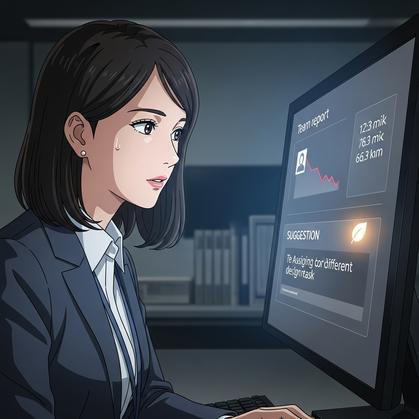
その日の午後。
佐藤は、マネージャー専用のダッシュボードを眺めていて、ハッとした。
『ワンチーム』から、彼女だけに見える「インサイトレポート」が届いていたのだ。
『分析レポート:高橋健太様について
・直近3日間のコードコミット(保存)頻度が、平均値より22%低下。
・キーボードのタイピングにおける修正率(バックスペースキーの使用率)が41%増加。
・チャットログにおいて、「すみません」「問題」「難しい」等の単語使用率が増加傾向にあります』
それは、高橋が「声に出せずにいるSOS」を、データが静かに可視化した瞬間だった。
佐藤がどうすべきかと思案していると、まるで彼女の心を見透かしたかのように、『ワンチーム』が動いた。
チーム全体のタスクボードに、新しい緊急タスクが追加される。
【タスク名:プロジェクトロゴとUIコンセプトの緊急ブラッシュアップ】
そして、佐藤にだけ、プライベートな通知が届いた。
『提案:上記タスクは、迅速かつ高品質なデザインスキルが求められます。
高橋様のスキルプロファイルは、本タスクの最適任者であることを示しています。
一時的に担当変更することで、現在のタスクにおけるパフォーマンス低下のリスクを緩和し、かつ緊急の要望にも応えることが可能です』
佐藤は、そのあまりに自然で、優しい解決策に、静かに感嘆した。
彼女はすぐに高橋の席へ向かう。
「高橋くん、ごめんなさい、急な話で。
クライアントから、どうしても今日中に、UIコンセプトをもう少し良くしてほしいって要望が入っちゃって。
デザインセンスが必要なこの仕事、高橋くんしか頼める人がいないの。
今の作業を一時中断して、こっちを助けてくれないかしら?」
それは、彼の能力を高く評価し、頼りにしているという、紛れもない事実だった。
高橋は、少し驚いた顔をしたが、「わかりました。やります」と、力強く頷いた。
第1-2-3話:“ありがとう”の循環

プレッシャーのかかるコーディングから一時的に解放された高橋は、別人のような集中力を発揮した。
UIデザインは、彼の最も得意で、好きな仕事だ。
彼は、楽しみながら、しかし猛烈な勢いで作業を進め、その日の夜までに、誰もが息をのむほど洗練されたデザイン案を完成させた。
翌朝。
佐藤が、その新しいデザイン案をクライアントに見せると、電話の向こうから、手放しの称賛が聞こえてきた。
佐藤はすぐに、チーム全員が見える『ワンチーム』のチャットチャンネルに書き込んだ。
「【朗報です!】
クライアントが、新しいUIコンセプトを絶賛していました!
これは、急な依頼にもかかわらず、最高の仕事をしてくれた高橋くんのおかげです。
高橋くん、本当にありがとう!」
そのメッセージに、チームのメンバーから、称賛のリアクションアイコンや、「すごい!」「さすがだね!」といったコメントが次々と続く。
高橋は、自分のデスクで、その感謝の連鎖を、少し照れくさそうに、しかし嬉しそうに眺めていた。
自分は、このチームに必要な人間なのだ。
その当たり前の事実が、乾いた心に温かく染み渡っていく。
コメントをお書きください